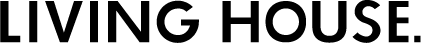天然木をふんだんに使用したナチュラルで温もりのあるデザインが特徴の家具メーカー「広松木工」とリビングハウス代表北村甲介による対談動画。広松木工の歴史から現在のデザインにたどり着くまでの過程、家具に対する想いなどを語ってもらいました。家具好きの方はもちろん、経営者、ビジネスマンにとっても必見の対談になりました。
天然木をふんだんに使用したナチュラルで温もりのあるデザインが特徴の家具メーカー「広松木工」とリビングハウス代表北村甲介による対談動画。広松木工の歴史から現在のデザインにたどり着くまでの過程、家具に対する想いなどを語ってもらいました。家具好きの方はもちろん、経営者、ビジネスマンにとっても必見の対談になりました。
プロフィール
広松木工
広松木工の家具作りの原点、それは、シンプルで装飾を排除した中から生まれる機能美が美しい「シェーカースタイル」です。広松木工のコンセプトは、シンプル・ナチュラル・機能的。シンプルなデザインは、木目や質感など木そのものの造形美を感じることができます。そして最後に、どこか懐かしいと感じたり、見て触れてほっとなごんだりという、使う人の琴線にふれるような、心に響く家具を作りたいと思っています。
対談動画
その1 その2対談

 北村- はい、それでは今日は広松木工の広松社長にお越しいただきました。よろしくお願いします。
広松- こちらこそよろしくお願いします。
北村- すいませんわざわざ遠くからお越しいただいて。ありがとうございます。
広松- はい(笑)
北村- 今日は色々と社長のこれまでの活動だとか、今後の広松木工さんがどういった方向に行くのか、そういった事を是非お伺いしたいなと思っております。
広松- はい、わかりました。
北村- で、まずはですね、広松木工さん、大体60年くらいの歴史だということなんですけども。これまでの流れ、経緯というものを少し教えていただけますか。
広松- はい。まあ僕、小さい時からね、あの、昔の大川ってのは徒弟制度がありまして、僕は兄弟が女ばっかりだったから、なんというのかな、住み込みの人たちがいるわけですよ、中学校出たばっかりの。その人達と寝泊まりをしながらね、一緒に生活してましたね。
北村- はい。
広松- 家と工場も一緒ですから、いつも機械の音と、トントンカンカンいう音とね、それでもうずっと大きくなってますものね。
北村- うーん。
広松- 親父がね、早く、僕13の時に死んだんで、男一人でしょ?だからお袋が、とりあえず大学までは出してあげるよと。あとは自分で決めなさいということでね、僕は大学出る時にどうしようかなって思ったけど、やっぱりものが作りたい。
北村- ああ、じゃあさっきの進路ですね。
広松- うん、進路決める時やっぱりね。やっぱりこう、染み付いてるんですよね。
北村- はい。
広松- だからやっぱり他の仕事じゃなくて、家具を作ろうというふうに思ったけど、大学出てそのまんま会社に入って。その頃ってのは木製の机だけを作ってた、会社って言っても町工場ですけどね。
北村- はい、それでは今日は広松木工の広松社長にお越しいただきました。よろしくお願いします。
広松- こちらこそよろしくお願いします。
北村- すいませんわざわざ遠くからお越しいただいて。ありがとうございます。
広松- はい(笑)
北村- 今日は色々と社長のこれまでの活動だとか、今後の広松木工さんがどういった方向に行くのか、そういった事を是非お伺いしたいなと思っております。
広松- はい、わかりました。
北村- で、まずはですね、広松木工さん、大体60年くらいの歴史だということなんですけども。これまでの流れ、経緯というものを少し教えていただけますか。
広松- はい。まあ僕、小さい時からね、あの、昔の大川ってのは徒弟制度がありまして、僕は兄弟が女ばっかりだったから、なんというのかな、住み込みの人たちがいるわけですよ、中学校出たばっかりの。その人達と寝泊まりをしながらね、一緒に生活してましたね。
北村- はい。
広松- 家と工場も一緒ですから、いつも機械の音と、トントンカンカンいう音とね、それでもうずっと大きくなってますものね。
北村- うーん。
広松- 親父がね、早く、僕13の時に死んだんで、男一人でしょ?だからお袋が、とりあえず大学までは出してあげるよと。あとは自分で決めなさいということでね、僕は大学出る時にどうしようかなって思ったけど、やっぱりものが作りたい。
北村- ああ、じゃあさっきの進路ですね。
広松- うん、進路決める時やっぱりね。やっぱりこう、染み付いてるんですよね。
北村- はい。
広松- だからやっぱり他の仕事じゃなくて、家具を作ろうというふうに思ったけど、大学出てそのまんま会社に入って。その頃ってのは木製の机だけを作ってた、会社って言っても町工場ですけどね。
 北村- 勉強机ですか?
広松- そうね、事務机とか勉強机とか、そんな感じ。
北村- ええ。
広松- ちょうどその頃にね、スチール製の家具が出始めたんですよ。事務机とかも全部ね。あれ一気に変わるんですね。時代が変わってしまったみたいになって。で、木製の机ってのがガッと落ち込みましてね。それまでは作れば売れるって状態でしたけど、それがもうなかなか売れなくなる。その頃にちょうど僕入ったんでね、どうしようっていう話ですよ。
北村- うーん。
広松- まず一番は箪笥(たんす)ですね。整理箪笥って言われる本当の箪笥ですよ。三尺六段とか昔言ってましたけどね。そういう机も作り始めたんですよね。両方やってました
けどね。まだまだ全てがダメになった訳ではなかったのでね。
北村- はい。
広松- でも、整理箪笥を作るとね、色んな物を作りたいという希望があるんです、自分の中にね。チャレンジ精神って言うとおかしいけどね。箪笥作りだったら、整理箪笥だけじゃなくて洋服箪笥も作ろうよ、っていう風にどんどんやっていこうとする訳ですね。トライしようとする訳。でも面白いのがね、現場の職人さんてね、保守的なんですね、非常に。だから箪笥作ってたのに洋服箪笥作るって、ちょっと抵抗する訳です。
北村- なるほど、はい。
広松- やってみれば簡単なんですけどね。職人さんたちだからやれるんですよ。
北村- 社長が入られる前からいらっしゃるような職人さん、昔気質の職人さんですね。
広松- そうそう、みんなそういう人ばっかりだったから。
北村- はい。
広松- でも、やろうよって説得して、やると出来るんですね。そうやって、整理箪笥、洋服箪笥、ちょっとした和箪笥って、単品のトータルみたいなものに動いていったんです。
北村- はい。
広松- そうやってる中でね、現在地が分からなかったんですよ。広松木工が現在どこにいるのか、自分がどこにいるのかよく分からなかったのでね。それまで、産業会館の展示会があるじゃないですか、あれとか出展したことなかったもんで。現在地を確認しようということで初めて出展してみたんですよ。
北村- それは何年ぐらい前ですか。
北村- 勉強机ですか?
広松- そうね、事務机とか勉強机とか、そんな感じ。
北村- ええ。
広松- ちょうどその頃にね、スチール製の家具が出始めたんですよ。事務机とかも全部ね。あれ一気に変わるんですね。時代が変わってしまったみたいになって。で、木製の机ってのがガッと落ち込みましてね。それまでは作れば売れるって状態でしたけど、それがもうなかなか売れなくなる。その頃にちょうど僕入ったんでね、どうしようっていう話ですよ。
北村- うーん。
広松- まず一番は箪笥(たんす)ですね。整理箪笥って言われる本当の箪笥ですよ。三尺六段とか昔言ってましたけどね。そういう机も作り始めたんですよね。両方やってました
けどね。まだまだ全てがダメになった訳ではなかったのでね。
北村- はい。
広松- でも、整理箪笥を作るとね、色んな物を作りたいという希望があるんです、自分の中にね。チャレンジ精神って言うとおかしいけどね。箪笥作りだったら、整理箪笥だけじゃなくて洋服箪笥も作ろうよ、っていう風にどんどんやっていこうとする訳ですね。トライしようとする訳。でも面白いのがね、現場の職人さんてね、保守的なんですね、非常に。だから箪笥作ってたのに洋服箪笥作るって、ちょっと抵抗する訳です。
北村- なるほど、はい。
広松- やってみれば簡単なんですけどね。職人さんたちだからやれるんですよ。
北村- 社長が入られる前からいらっしゃるような職人さん、昔気質の職人さんですね。
広松- そうそう、みんなそういう人ばっかりだったから。
北村- はい。
広松- でも、やろうよって説得して、やると出来るんですね。そうやって、整理箪笥、洋服箪笥、ちょっとした和箪笥って、単品のトータルみたいなものに動いていったんです。
北村- はい。
広松- そうやってる中でね、現在地が分からなかったんですよ。広松木工が現在どこにいるのか、自分がどこにいるのかよく分からなかったのでね。それまで、産業会館の展示会があるじゃないですか、あれとか出展したことなかったもんで。現在地を確認しようということで初めて出展してみたんですよ。
北村- それは何年ぐらい前ですか。
 広松- ええとねえ、僕が26,7くらいの時じゃないかな。会社に入って4,5年くらい経った頃でしょうね。
北村- はい。
広松- ただ見事にね、誰も立ち止まってくれんです。商品力、営業力、価格訴求力、デザイン力、ないない尽くしですよ。たまに立ち止まってくれる人が、取引のある所がね、おっ珍しいななんていう感じですよ。で、まさに分かりましたね。ないない尽くしだって。あ、これが広松の現在地だって。という所が出発点です。
北村- なるほど。
広松- 現在地が分かった。で、どうする。まず立ち止まってもらうしかないんじゃない。広松の名前を覚えてもらうしかないじゃない。そこでどうするってなった時に、デザインと、素材って言うのかな、で名
前を知ってもらうしかない。そう思って、30ちょっと前かな、デザイナーさんと契約して。
北村- はい。
広松- ええとねえ、僕が26,7くらいの時じゃないかな。会社に入って4,5年くらい経った頃でしょうね。
北村- はい。
広松- ただ見事にね、誰も立ち止まってくれんです。商品力、営業力、価格訴求力、デザイン力、ないない尽くしですよ。たまに立ち止まってくれる人が、取引のある所がね、おっ珍しいななんていう感じですよ。で、まさに分かりましたね。ないない尽くしだって。あ、これが広松の現在地だって。という所が出発点です。
北村- なるほど。
広松- 現在地が分かった。で、どうする。まず立ち止まってもらうしかないんじゃない。広松の名前を覚えてもらうしかないじゃない。そこでどうするってなった時に、デザインと、素材って言うのかな、で名
前を知ってもらうしかない。そう思って、30ちょっと前かな、デザイナーさんと契約して。
北村- はい。
 広松- 最初森さんじゃなかったんです。そうやってデザイナー取り込んで、要するにソフトにお金を払うというのかな。その当時、うちぐらいの規模じゃまずそういう事やってなかったと思うんです。でもやはり、立ち止まってもらう、名前を覚えてもらうためには、やっぱりデザイン、要するに自分じゃできないから、お願いしてやろうということです。
北村- その当時ソフトというフィーにお金を投下するって、なかなか勇気が要ったことだと思うんですけど。
広松- 最初森さんじゃなかったんです。そうやってデザイナー取り込んで、要するにソフトにお金を払うというのかな。その当時、うちぐらいの規模じゃまずそういう事やってなかったと思うんです。でもやはり、立ち止まってもらう、名前を覚えてもらうためには、やっぱりデザイン、要するに自分じゃできないから、お願いしてやろうということです。
北村- その当時ソフトというフィーにお金を投下するって、なかなか勇気が要ったことだと思うんですけど。
 広松- そうですね、難しいですね。そうやってやり始めて、曲げないというのかな、ブレないようにしようと、目指す所を決めながら、デザイン、品質、機能性、それとうちの場合はどっかにこう、優しさというのかな、郷愁感みたいなものをどっかに感じさせるようなものを作るというのがありましてね。
北村- 今の製品の流れはその時から。
広松- そう、そんな感じですね。で、一番最初にミラノ・サローネに行ったのは30ちょっとでしたか。初めて行ったんですけど、サローネの会場でイタリアモダーンって言われる前衛的なものと、クラシックなものとありましてね。どちらも凄くインパクトがあったんです。でも僕はどっちかというとクラシックの、デザインをきっちりとやられてるものはね、何百年経っても我々の心を打つなってものがあって。で、帰ってきた時にちょうど森さんと知り合ってね。いろんな話をしてる中で、契約してやっていこうという話になって。
じゃあどういう風にしたらいいなって色んな事を侃々諤々やった訳です。その時に僕は、クラシックなものって言うとおかしいな、ちゃんと技術とデザインとそれに裏打ちされたものが物凄いインパクトあったって話をしたら、僕も自分の広松木工が存続する限りはずっと作り続けて行けるような製品開発を一緒にやってほしいって依頼してね。大きくなくてもいいんだけど、コンパクトでいいんだけど、インパクトのある会社にしたいっていう風に思って森さんと話してね。だったらシェーカーしかないんじゃないって話になったんですよ。
北村- はい。
広松- もう200年も前のスタイルが、今でもこの空間においても違和感なく収まる。人を和ませてくれる。じゃあもうシェーカーを基本にしようと、森さんと最初に契約した時に、シェーカーを一番最初のアイテムにした訳ですよ。それもね、形を真似ようとかいうのもあったけど、どこまで復元できるかやってみようっていう捉え方をしたね。よく味を"なになに風"ってぱくってるのがあるじゃないですか。ぱくるのもいいけどね、どこまでできるか一回やってみようよという話しでね。やり始めたんですよ。何回か改良しながらですけど、それが一つのうちの開発の基準っていうのかな。シンプルで、ナチュラルで、機能的で、無駄は省いて、どっかにほっとさせる懐かしい感じがあるってのもシェーカーだから。その外面を基にしながら今後の開発を進めていこうねってのは森さんとの合言葉みたいになって、それから色んな物を作っていった訳です。
北村- はい。
広松- そうなるとね、うちの商品を見てもらえば分かると思いますけども、いろんなスタイルがあるけど、なんかまとまってるというか、基準がそこにあるんでそんなにブレない。売りたいからこういう物を作るんじゃなくてね、自分たちの世界とか、要するに自分の好きなものなんです。自分のセンスとしてこれは自分の好きな世界と思うものを追加していってる。増やして行ってる。というのがうちの進んでるところかな。
北村- シェーカーで進んでいこうとした時の、当時のお客さんの反応はどうだったんですか。
広松- 非常にインパクトはありましたよ。ここまでやったかってくらい沢山みんなに見てもらったけど、手を出してくれる人は少なかったですね。その当時二件くらい。
北村- 展示会とか。
広松- そうですね、難しいですね。そうやってやり始めて、曲げないというのかな、ブレないようにしようと、目指す所を決めながら、デザイン、品質、機能性、それとうちの場合はどっかにこう、優しさというのかな、郷愁感みたいなものをどっかに感じさせるようなものを作るというのがありましてね。
北村- 今の製品の流れはその時から。
広松- そう、そんな感じですね。で、一番最初にミラノ・サローネに行ったのは30ちょっとでしたか。初めて行ったんですけど、サローネの会場でイタリアモダーンって言われる前衛的なものと、クラシックなものとありましてね。どちらも凄くインパクトがあったんです。でも僕はどっちかというとクラシックの、デザインをきっちりとやられてるものはね、何百年経っても我々の心を打つなってものがあって。で、帰ってきた時にちょうど森さんと知り合ってね。いろんな話をしてる中で、契約してやっていこうという話になって。
じゃあどういう風にしたらいいなって色んな事を侃々諤々やった訳です。その時に僕は、クラシックなものって言うとおかしいな、ちゃんと技術とデザインとそれに裏打ちされたものが物凄いインパクトあったって話をしたら、僕も自分の広松木工が存続する限りはずっと作り続けて行けるような製品開発を一緒にやってほしいって依頼してね。大きくなくてもいいんだけど、コンパクトでいいんだけど、インパクトのある会社にしたいっていう風に思って森さんと話してね。だったらシェーカーしかないんじゃないって話になったんですよ。
北村- はい。
広松- もう200年も前のスタイルが、今でもこの空間においても違和感なく収まる。人を和ませてくれる。じゃあもうシェーカーを基本にしようと、森さんと最初に契約した時に、シェーカーを一番最初のアイテムにした訳ですよ。それもね、形を真似ようとかいうのもあったけど、どこまで復元できるかやってみようっていう捉え方をしたね。よく味を"なになに風"ってぱくってるのがあるじゃないですか。ぱくるのもいいけどね、どこまでできるか一回やってみようよという話しでね。やり始めたんですよ。何回か改良しながらですけど、それが一つのうちの開発の基準っていうのかな。シンプルで、ナチュラルで、機能的で、無駄は省いて、どっかにほっとさせる懐かしい感じがあるってのもシェーカーだから。その外面を基にしながら今後の開発を進めていこうねってのは森さんとの合言葉みたいになって、それから色んな物を作っていった訳です。
北村- はい。
広松- そうなるとね、うちの商品を見てもらえば分かると思いますけども、いろんなスタイルがあるけど、なんかまとまってるというか、基準がそこにあるんでそんなにブレない。売りたいからこういう物を作るんじゃなくてね、自分たちの世界とか、要するに自分の好きなものなんです。自分のセンスとしてこれは自分の好きな世界と思うものを追加していってる。増やして行ってる。というのがうちの進んでるところかな。
北村- シェーカーで進んでいこうとした時の、当時のお客さんの反応はどうだったんですか。
広松- 非常にインパクトはありましたよ。ここまでやったかってくらい沢山みんなに見てもらったけど、手を出してくれる人は少なかったですね。その当時二件くらい。
北村- 展示会とか。
 広松- 展示会に出店して、二件くらいのところがよしやってみようかって言ってくれまして。その当時ってお披露目してもらう場所がないじゃないですか。店舗でお披露目してもらうしかエンドユーザーに届く術がないもんでね、悶々としてたんです。その当時から会長はね、これは絶対この路線しかないバイって言ってくれたんです。ヨイショじゃないけどね。二人だけだったんです。北村会長と、原家具さんっていうのがあってね。
北村- はい、九州の。
広松- そう九州の。もうないけどね、残念ながら。あそこの社長が二人、広松さんこの路線、絶対これしかないばい、頑張ってやりなさいよって言ってくれたのがずっと励みですよ。
北村- 二十何年か前。
広松- もう二十五年以上前かな。世の中ガンガン良かったじゃないですか。沢山作ればもっと儲かるって時代だから。でもうちは逆に行ったんです。あれはもう、味の追求だから。沢山の人に買ってもらうのは無理な商品に入っていった訳ね。だからなかなか会社は苦しかったけど、辛抱して続けて、これでもかこれでもかと我慢してやってると周りがどんどんどんどん、本気でやるつもりやなみたいなところがあってね。で徐々に広がっていく。
北村- 広がっていって、よっしゃ間違いなくこれで大丈夫だと思えたのは、どれくらい期間がありました?
広松- うーん、十五年くらい。ここ十年くらいなんとかこれでやっていけるなと思ってます。だから十五年くらい。森さんとも話すけどね、売れないのがいっぱいあるわけですよ。開発はしたけどね。多分うちが一番森さんの中で開発してると思う。自分はこんだけあるよって常に森さんも言うけどね。それの上に成り立ってる。
北村- はい。
広松- 展示会に出店して、二件くらいのところがよしやってみようかって言ってくれまして。その当時ってお披露目してもらう場所がないじゃないですか。店舗でお披露目してもらうしかエンドユーザーに届く術がないもんでね、悶々としてたんです。その当時から会長はね、これは絶対この路線しかないバイって言ってくれたんです。ヨイショじゃないけどね。二人だけだったんです。北村会長と、原家具さんっていうのがあってね。
北村- はい、九州の。
広松- そう九州の。もうないけどね、残念ながら。あそこの社長が二人、広松さんこの路線、絶対これしかないばい、頑張ってやりなさいよって言ってくれたのがずっと励みですよ。
北村- 二十何年か前。
広松- もう二十五年以上前かな。世の中ガンガン良かったじゃないですか。沢山作ればもっと儲かるって時代だから。でもうちは逆に行ったんです。あれはもう、味の追求だから。沢山の人に買ってもらうのは無理な商品に入っていった訳ね。だからなかなか会社は苦しかったけど、辛抱して続けて、これでもかこれでもかと我慢してやってると周りがどんどんどんどん、本気でやるつもりやなみたいなところがあってね。で徐々に広がっていく。
北村- 広がっていって、よっしゃ間違いなくこれで大丈夫だと思えたのは、どれくらい期間がありました?
広松- うーん、十五年くらい。ここ十年くらいなんとかこれでやっていけるなと思ってます。だから十五年くらい。森さんとも話すけどね、売れないのがいっぱいあるわけですよ。開発はしたけどね。多分うちが一番森さんの中で開発してると思う。自分はこんだけあるよって常に森さんも言うけどね。それの上に成り立ってる。
北村- はい。
 広松- もう一つ思うのがね、こんだけやったってことはこんだけ作ったって訳です。こんだけ作ったノウハウとかセンスというものがうちの社員の中に残ってるわけです。社員が気づいてない。この頃いつも言うんだけど、工場の中にいたらよう分からんかも知れんけど、あんたたちの手の中にはそういうのが蓄積されて、ちゃんと認めてもらえるところまで来てるんだよと言うんやけど、まだよく分かってないかも知れない。社長とかにそう言っていただくと、それを伝えたいんだね。なかなかそれができん。
北村- そいうえば今日、今これを抑えていただいてるGALAも広松さんの所のものですけど、もう長いんですよね。例えばこのGALAってどういったものに特徴があるんでしょう。
広松- これはね、シェーカースタイルがまずあって、一年に一個ずつうちのメインになるうるような気の長い商品をやってこうという風に思った訳です。で、シェーカースタイルをやって一年後に、森さんがサンタフェスタイルっていうデザイン本を持ってきたんです。広松さんこれどうやろって。僕も最初はね、ちょっと異質じゃないですか、この手触りとかこの仕上げ方とか、今までにない。森さんは枯れた感じが良いんだって言うの。枯れた感じ、すごいね~ってね。で、半信半疑だったけど、森さんと一緒にやってくとなかなか良い味になってくる訳です。これからサンタフェスタイルというのをスタートさせて、あれが出てきたわけです。あれはその中の延長線でF1ってのが出てきたわけですけどね。ニッチな商品みたいだけど、潜在的に需要はあったんだけど、ユーザーさんの目に提案できたなかったみたいな、そういうものかな。非常にこれは爆発的に売れました。
北村- 我々のお店でも、先ほど仰っていただいたものもそうですけど、すごく安定的なお客様の人気があるんですけど、ここ数年、より特に若い感度の高い方を中心にして広松さんのところの商品を気に入られる方が非常に多い感じなんですね。
広松- もう一つ思うのがね、こんだけやったってことはこんだけ作ったって訳です。こんだけ作ったノウハウとかセンスというものがうちの社員の中に残ってるわけです。社員が気づいてない。この頃いつも言うんだけど、工場の中にいたらよう分からんかも知れんけど、あんたたちの手の中にはそういうのが蓄積されて、ちゃんと認めてもらえるところまで来てるんだよと言うんやけど、まだよく分かってないかも知れない。社長とかにそう言っていただくと、それを伝えたいんだね。なかなかそれができん。
北村- そいうえば今日、今これを抑えていただいてるGALAも広松さんの所のものですけど、もう長いんですよね。例えばこのGALAってどういったものに特徴があるんでしょう。
広松- これはね、シェーカースタイルがまずあって、一年に一個ずつうちのメインになるうるような気の長い商品をやってこうという風に思った訳です。で、シェーカースタイルをやって一年後に、森さんがサンタフェスタイルっていうデザイン本を持ってきたんです。広松さんこれどうやろって。僕も最初はね、ちょっと異質じゃないですか、この手触りとかこの仕上げ方とか、今までにない。森さんは枯れた感じが良いんだって言うの。枯れた感じ、すごいね~ってね。で、半信半疑だったけど、森さんと一緒にやってくとなかなか良い味になってくる訳です。これからサンタフェスタイルというのをスタートさせて、あれが出てきたわけです。あれはその中の延長線でF1ってのが出てきたわけですけどね。ニッチな商品みたいだけど、潜在的に需要はあったんだけど、ユーザーさんの目に提案できたなかったみたいな、そういうものかな。非常にこれは爆発的に売れました。
北村- 我々のお店でも、先ほど仰っていただいたものもそうですけど、すごく安定的なお客様の人気があるんですけど、ここ数年、より特に若い感度の高い方を中心にして広松さんのところの商品を気に入られる方が非常に多い感じなんですね。
 広松- ありがとうございます。
北村- 時代をだいぶ先を行かれてて、っていう風に感じるんですけど、今の状況ってどうお考えですか。
広松- 僕ね、国籍も関係ないし、年代も関係ないと思うんですよ。琴線に触れるっていうのかな。目指すところは琴線に作用するような力のあるものじゃないと、これからのお客様って、こういう時代だし、なかなかお金も出してくれんと思うんです。本質的なところにきちんと届くようなものじゃないと認めてもらえなくなってきたんかなって気はしますね。年配の方も、結構守備範囲が広いです。
北村- 広いですねえ。本当にそうです。
広松- そういう意味では若者の人たちにも確かになんて言ってもらえるのは非常に嬉しいし。基本的に自分たちの好きなもの、自分たちの世界を作ろうと思ってやってる訳だから、お客様になってくれるとその人はもう仲間っていうかね、もう一つ入り込んだ人になってしまうというのかな。
北村- ということは、こういった人に使ってもらいたいというよりも、こんな使い方をして欲しいという...
広松- 理解して欲しいっていうのかね。我々の考えを分かってほしいって感じですよ。その為に、機能的なことは余り言わないですよね。機能的ってよりも、味。
北村- 味。あと使い心地ってのもそうですね。
広松- 味の追求みたいなところでね、この味分かってくれる?って感じですよ。そんな感じで今後の開発はやって行きたいなと思ってますけどね。
北村- 今後のものづくりとしてのこだわりとか、自分たちの世界というものは曲げずに進んでいくということですよね。
広松- ありがとうございます。
北村- 時代をだいぶ先を行かれてて、っていう風に感じるんですけど、今の状況ってどうお考えですか。
広松- 僕ね、国籍も関係ないし、年代も関係ないと思うんですよ。琴線に触れるっていうのかな。目指すところは琴線に作用するような力のあるものじゃないと、これからのお客様って、こういう時代だし、なかなかお金も出してくれんと思うんです。本質的なところにきちんと届くようなものじゃないと認めてもらえなくなってきたんかなって気はしますね。年配の方も、結構守備範囲が広いです。
北村- 広いですねえ。本当にそうです。
広松- そういう意味では若者の人たちにも確かになんて言ってもらえるのは非常に嬉しいし。基本的に自分たちの好きなもの、自分たちの世界を作ろうと思ってやってる訳だから、お客様になってくれるとその人はもう仲間っていうかね、もう一つ入り込んだ人になってしまうというのかな。
北村- ということは、こういった人に使ってもらいたいというよりも、こんな使い方をして欲しいという...
広松- 理解して欲しいっていうのかね。我々の考えを分かってほしいって感じですよ。その為に、機能的なことは余り言わないですよね。機能的ってよりも、味。
北村- 味。あと使い心地ってのもそうですね。
広松- 味の追求みたいなところでね、この味分かってくれる?って感じですよ。そんな感じで今後の開発はやって行きたいなと思ってますけどね。
北村- 今後のものづくりとしてのこだわりとか、自分たちの世界というものは曲げずに進んでいくということですよね。
 広松- より明確にしていく、我々の塊というのかな、もっともっと突き詰めていく。その為にはお店も必要なんです。今は福岡にもあるけど、自分たちの世界じゃないですか。それはどこもそうですけど、自分たちの世界を創りあげてらっしゃるわけだから。我々は我々の世界を創り上げて行く。で、それを確認するためには、そういう空間が必要なんですね。
家具を物で見るんじゃなくて、引いてみるっていうの?一個一個じゃなくて、シーンとして捉えていく。どう収めていくか、収まるのかみたいなね、それが大事であって。どこどこのナントカ家具屋さんの中で買った負けたじゃないじゃないですか。住む人達の空間の中にきちっと収まるかどうか。これが勝負じゃないかなって、今思ってますね。そういう風な、ちょっと引いてみると、気づかなかったところが見えるような気が、この頃してます。
北村- うーん。
広松- たまに僕も配達行くんです。近郊で僕がおすすめした人なんかの所にいくんですけどね。そうすると、どう収まってるか見れるじゃないですか。今まで家具メーカーってそれ見れなかったんですね。全部販売店さん、問屋さんの情報を基に色んな物を作っていった。これから先の、もっと大事な部分が、作るだけじゃなくてね、納めて、その後またメンテナンスきちっとして行く、お付き合いして行く。その後が長いってことがはっきり分かりましたね。
北村- はい。
広松- 我々ここまでで終わってたなというのが反省点でした。こっからまたずっと大事なことが分かり始めたんで。品質の問題、使う金具にしてもより安心して長く使っていただけるもの。そういう風に社内の考え方も変えて行こうとしてるとこなんですけど。なかなか難しいですけどね。
北村- 今一番困ってらっしゃることとか、迷ってらっしゃることはありますか。
広松- 森さんと、こんなテイストの会社にしていこうとやってきたけど、それを次の世代に伝えていかなければならないじゃないですか。次の世代に次の世代に伝えて行かなければならないけど、どうそれを受け継いで行ってもらうかというのは、なかなか簡単そうで簡単でないんですよね。
北村- はい。
広松- 会社って自分たちの作りだしたものを責任持ってかないとだめだっていうのがあるんで、その為に会社もしっかり残っとかないかん訳ですよ。その為には皆がしっかりしとかないかんし、考え方とか、技術とか、デザインセンスみたいなものがちゃんと引き継がれて行かなければならないんです。森さんも僕も寿命来るし、そうしたときどうするっていうところをね、社内にちゃんとやる人間を育てておかないと会社は衰退してくと思うんです。そこが一番悩んでるというのかな。そこに力を入れないといかんなってのを、北村さんにこの前もこっち来てもらった時いろいろ話し聞かせてもらったけど、そういうことですよ。
北村- はい。
広松- 社員教育というとちょっとボワーっとなってしまうけどね、そういうのは一番大事かなと思ってますね。
北村- ものの作る方向性はいつでもきちっと決まってるわけですね。
広松- より明確にしていく、我々の塊というのかな、もっともっと突き詰めていく。その為にはお店も必要なんです。今は福岡にもあるけど、自分たちの世界じゃないですか。それはどこもそうですけど、自分たちの世界を創りあげてらっしゃるわけだから。我々は我々の世界を創り上げて行く。で、それを確認するためには、そういう空間が必要なんですね。
家具を物で見るんじゃなくて、引いてみるっていうの?一個一個じゃなくて、シーンとして捉えていく。どう収めていくか、収まるのかみたいなね、それが大事であって。どこどこのナントカ家具屋さんの中で買った負けたじゃないじゃないですか。住む人達の空間の中にきちっと収まるかどうか。これが勝負じゃないかなって、今思ってますね。そういう風な、ちょっと引いてみると、気づかなかったところが見えるような気が、この頃してます。
北村- うーん。
広松- たまに僕も配達行くんです。近郊で僕がおすすめした人なんかの所にいくんですけどね。そうすると、どう収まってるか見れるじゃないですか。今まで家具メーカーってそれ見れなかったんですね。全部販売店さん、問屋さんの情報を基に色んな物を作っていった。これから先の、もっと大事な部分が、作るだけじゃなくてね、納めて、その後またメンテナンスきちっとして行く、お付き合いして行く。その後が長いってことがはっきり分かりましたね。
北村- はい。
広松- 我々ここまでで終わってたなというのが反省点でした。こっからまたずっと大事なことが分かり始めたんで。品質の問題、使う金具にしてもより安心して長く使っていただけるもの。そういう風に社内の考え方も変えて行こうとしてるとこなんですけど。なかなか難しいですけどね。
北村- 今一番困ってらっしゃることとか、迷ってらっしゃることはありますか。
広松- 森さんと、こんなテイストの会社にしていこうとやってきたけど、それを次の世代に伝えていかなければならないじゃないですか。次の世代に次の世代に伝えて行かなければならないけど、どうそれを受け継いで行ってもらうかというのは、なかなか簡単そうで簡単でないんですよね。
北村- はい。
広松- 会社って自分たちの作りだしたものを責任持ってかないとだめだっていうのがあるんで、その為に会社もしっかり残っとかないかん訳ですよ。その為には皆がしっかりしとかないかんし、考え方とか、技術とか、デザインセンスみたいなものがちゃんと引き継がれて行かなければならないんです。森さんも僕も寿命来るし、そうしたときどうするっていうところをね、社内にちゃんとやる人間を育てておかないと会社は衰退してくと思うんです。そこが一番悩んでるというのかな。そこに力を入れないといかんなってのを、北村さんにこの前もこっち来てもらった時いろいろ話し聞かせてもらったけど、そういうことですよ。
北村- はい。
広松- 社員教育というとちょっとボワーっとなってしまうけどね、そういうのは一番大事かなと思ってますね。
北村- ものの作る方向性はいつでもきちっと決まってるわけですね。
 広松- もう決まってるつもりです。これはもう多分ブレないでしょう。ただ、さっき言ったように、単体のものを見るんじゃなくて、あくまでもシーンの中に備わってるという捉え?方で、ずーっと引きながら考えてものを作っていく。小さな物もあるじゃないですか。バッグもあったりね。そういう風にどんどん動くでしょ、全部。もっと一つの空間、生活に対して我々はどう貢献、提案していけるか。よそが出来ないようなことをバッとやれるかが、うちのやるべきところかな。あまりみんな冒険したがらないけど、僕なんかあまり計算できないから。計算するよりも先にやってしまってね、それからって考え方なんでね。やってしまって、それから考えようみたいなところが結構あるんです。
北村- はい。
広松- そういう意味では、味の追求と、味をどう社内につなげていくかですね。
北村- 今日は本当に長いことお付き合いいただきましてありがとうございました。我々LIVING HOUSEも長いお付き合いさせていただいてますけども、今後とも長いお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
広松- こちらこそよろしくお願いします。
北村- どうもありがとうございました。
広松- もう決まってるつもりです。これはもう多分ブレないでしょう。ただ、さっき言ったように、単体のものを見るんじゃなくて、あくまでもシーンの中に備わってるという捉え?方で、ずーっと引きながら考えてものを作っていく。小さな物もあるじゃないですか。バッグもあったりね。そういう風にどんどん動くでしょ、全部。もっと一つの空間、生活に対して我々はどう貢献、提案していけるか。よそが出来ないようなことをバッとやれるかが、うちのやるべきところかな。あまりみんな冒険したがらないけど、僕なんかあまり計算できないから。計算するよりも先にやってしまってね、それからって考え方なんでね。やってしまって、それから考えようみたいなところが結構あるんです。
北村- はい。
広松- そういう意味では、味の追求と、味をどう社内につなげていくかですね。
北村- 今日は本当に長いことお付き合いいただきましてありがとうございました。我々LIVING HOUSEも長いお付き合いさせていただいてますけども、今後とも長いお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
広松- こちらこそよろしくお願いします。
北村- どうもありがとうございました。
Contact
各種お問い合わせ

Company
会社概要